【人手不足を防ぐための対策も必要】
令和7年度の最低賃金の目安が発表され、全都道府県で最低賃金が1,000円を超え全国加重平均で63円引きあがる目安です。これは過去最大の引き上げ幅となり、特に中小企業にとって大きな影響が予想されます。最低賃金の改定は、企業の賃金体系や人材確保に直接関わる重要なテーマです。この記事では、最低賃金引き上げに備えて企業が準備すべきポイントをわかりやすく解説します。
- 時給制従業員の賃金見直し
最低賃金を下回る賃金を支払うことは法令違反となります。以下を確認・対応しましょう
・現在の時給チェック:すべての時給制従業員の賃金を確認し、新たな最低賃金を下回っていないか検証します。
・賃金調整:最低賃金を下回る場合、速やかに時給を改定。従業員とのコミュニケーションも忘れずに行い、変更内容を丁寧に説明しましょう。
- 月給制従業員の賃金見直し
月給制の場合も、最低賃金への対応が必要です
・時給換算の計算:月給を年間の平均所定労働時間で割り、時給換算額を算出します。この金額が新しい最低賃金を下回らないか確認してください。
・調整の実施:必要に応じて月給の見直しを行い、従業員のモチベーション維持にも配慮しましょう。
- 所得税の扶養範囲内勤務者への対応
扶養内で働く従業員への影響も見逃せません
・勤務時間調整の協議:(所得税の扶養範囲)以内で働く従業員に対し、12月までの勤務時間や来年以降の働き方について早めに話し合いましょう。
・柔軟な対応:従業員の希望に応じてシフトや労働時間を調整し、働きやすい環境を整えることが重要です。
- 社会保険の扶養範囲内勤務者への対応
社会保険の扶養範囲(年収130万円未満、または19~23歳の一部対象者は150万円未満)で働く従業員にも注意が必要です
・シフト調整の検討:年収上限を超えないよう、シフトや労働時間の見直しを提案。従業員の生活スタイルに合わせた柔軟な対応が求められます。
・事業主証明の活用:130万円の壁を超える場合、最大2回まで事業主証明により一時的な収入超過を認め、扶養資格を維持できる場合があります。この制度を活用し、従業員の不安を軽減しましょう。
- 人手不足への備え
最低賃金の引き上げは、従業員の確保にも影響を与えます。以下の対策を検討してください
・採用計画の見直し:賃金改定に伴うコスト増を踏まえ、採用人数や条件を再検討。
・従業員の定着策:賃金だけでなく、働きやすい環境や福利厚生の充実を図り、離職を防ぎましょう。
・早めの準備:急な人手不足を防ぐため、早い段階でのシフト調整や採用活動を進めることが重要です。
まとめ
最低賃金の引き上げは、企業にとってコスト管理や人材確保の大きな課題です。しかし、早めの準備と適切な対応により、従業員の満足度を維持しつつ、法令遵守を実現できます。特に、賃金の見直しや扶養範囲内の従業員とのコミュニケーション、採用戦略の再構築は急務となります。

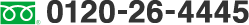
![[ご相談無料]まずはお気軽にご連絡ください。TEL:0120-26-4445[受付時間平日10:00〜21:00(土日祝日は休み)]](https://www.j-consulting.jp/wp-content/themes/theme-yuhara2/img/contact.png)

