短時間や単発の労働契約で働く、いわゆる「スポットワーク」の利用者数が急増しています。
スポットワークにはさまざまな形態がありますが、“雇用仲介アプリ”を使って仕事のマッチングや賃金の立替払をするタイプの利用が特に増えているようです。労働者にとっては隙間時間を活用して収入を得ることに使えたり、事業主にとっては急に人手が欲しくなった時に活用できたりして便利です。
しかし、利用の増加に伴って、スポットワーク利用者から労働基準監督署への相談や申告も寄せられるようになってきています。
そこで、厚生労働省では、スポットワークを利用する時のポイントをまとめたリーフレットを労働者向けと事業者向けにそれぞれ作成し、公表しました。
リーフレットに記載されている内容のうち、労働契約の成立時期と休業手当、平均賃金について解説します。
労働契約の成立時期について
労働契約が成立すると、労働に関する法律が適用されるようになります。
雇用契約は「事業主」と「労働者(スポットワーカー)」で結ばれる
スポットワーク仲介事業者は職業の紹介をするだけで、雇用契約は「事業主」と「労働者(スポットワーカー)」の間で結ばれます。
労働条件の明示、雇入れ時の安全衛生教育、労災が起きた場合の給付など、事業主が行う必要があります。
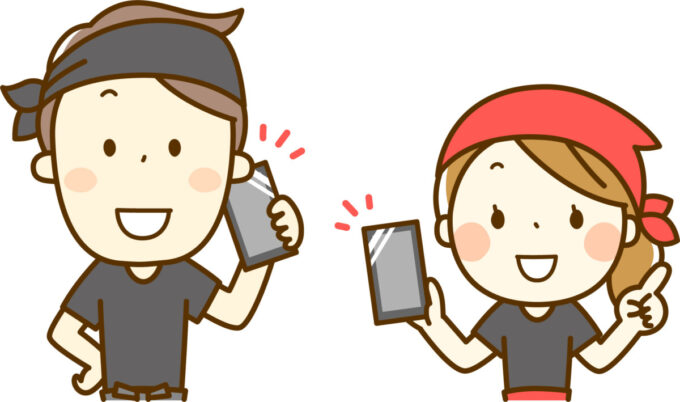
いつ契約が成立するのか
トラブルを避けるためにも、労使どちらも「いつ契約が成立するのか」という認識を共有したうえで労働契約をする必要があります。
スポットワークでは、雇用仲介アプリを使って、事業主が掲載した求人に労働者が応募して、面接等をせずに短時間にその求人と応募がマッチングすることが一般的です。
一般社団法人スポットワーク協会は、面接等を経ずに先着順で就労が決定するかたちのスポットワークにおいて『働き手が求人に応募を完了した時点で、解約権が留保された労働契約(解約権留保付労働契約)が成立する』という考え方に基づいて、2025年9月1日以降、各社が順次必要な対応を進めていくことを公表しています。
労働契約法
第6条(労働契約の成立)
労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。
労働契約が成立したあとに労働日や労働時間等を変更する場合は、労働条件の変更をするということになるので、事業主とスポットワーカー双方の合意が必要です。
また、労働契約が成立した後に事業主の都合で仕事をキャンセルする場合は特に注意が必要です。
休業手当の支払い
労働契約が成立した後に、労働者は労働をする意思があるにも関わらず、事業主の都合で仕事をキャンセルしたり早上がりさせたりすることになった場合、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当します。
事業主の都合で労働者を休業させた場合、事業主は最低でも労働者に休業手当(平均賃金の6割以上)を支払う必要があります。
民法との関係
民法536条2項の規定により、使用者に責任を負うべき理由や落ち度がある場合は労働者は賃金の全額を受ける権利を失わないことになりますが、民法の規定は当事者の合意でその適用をしないこともできる任意規定です。
民法(債務者の危険負担等)
第536条 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
一方、労働基準法の休業手当は該当する場合は必ず支払わなければいけません。
早上がりをさせて実働時間のみ給与を払う場合で、その金額が休業手当(平均賃金の6割)に満たない場合も、差額を追加して支払うことで、休業手当の金額は保障する必要があります。
休業手当とは
使用者の都合によって労働者を休ませた場合、平均賃金の6割以上の額を支払わなければいけませんが、この手当を休業手当といいます。
労働基準法(休業手当)
第26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
休業手当は、労働者の最低限の生活を保障するための規定です。
そのため、天災事変等でどうしようもなかった時(不可抗力)に該当しない限り使用者の都合として考えられ、親会社の経営難のための資金・資材の獲得困難や、業務量減少に伴う休業なども使用者の都合に該当します。
休業手当を支払わなかった場合、労働基準法第120条に基づいて30万円以下の罰金が科される可能性があります。
平均賃金の計算
労働基準法で定められている平均賃金は、次の計算方法で求めます。
「算定すべき事由の発生した日以前の3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額」
÷「その期間の総日数」
雇入れ初日の平均賃金の計算
単発のスポットワークがキャンセルされる場合、「雇入れ初日のキャンセル」ということも考えられますが、この場合は「算定すべき事由の発生した日以前の3か月間」がないため上記の方法では計算ができません。
この場合、通達(昭和22年9月13日 発基17号)の計算方法が参照できます。
労働基準法の施行に関する件 (昭和二二年九月一三日)(発基第一七号)(都道府県労働基準局長あて労働次官通達)
雇い入れの日に平均賃金を算定すべき事由が発生した場合には、当該労働者に対し一定額の賃金が予め定められてゐる場合には、その額により推算し、しからざる場合には、その日に、当該事業場において、同一業務に従事した労働者の一人平均の賃金額により推算すること。
「当該労働者に対し一定額の賃金が予め定められてゐる場合には、その額により推算」とあるので、その日に働いて支給される予定だった給与額を基に休業手当を計算するようになります。

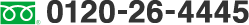
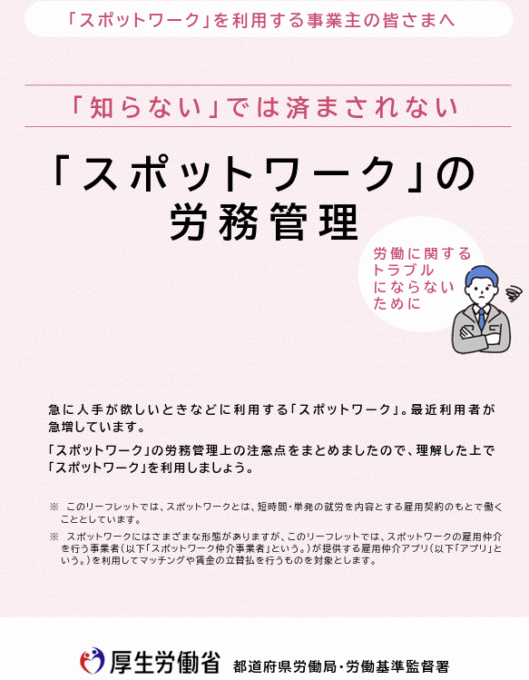
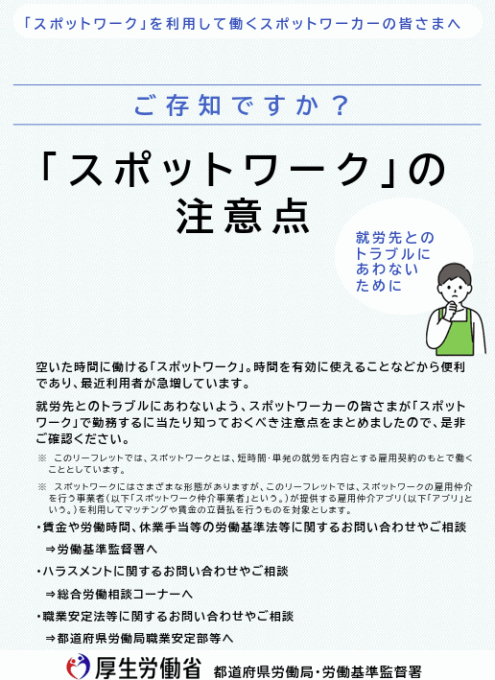


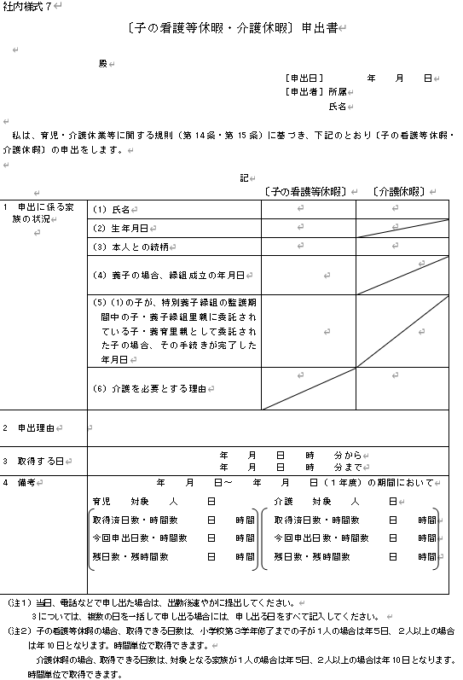

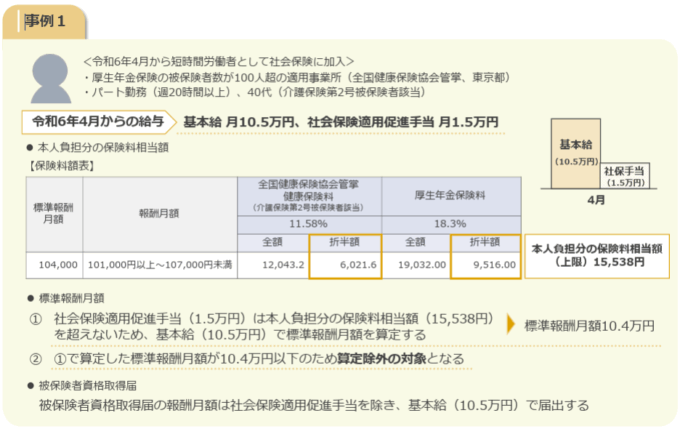
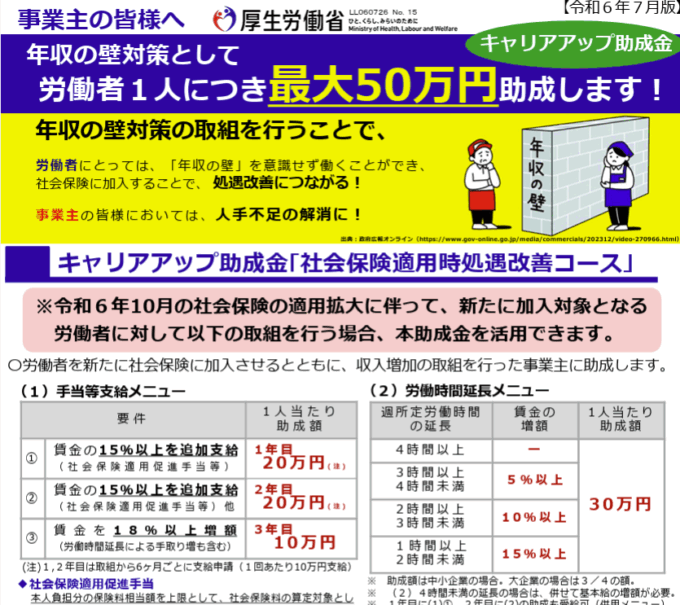


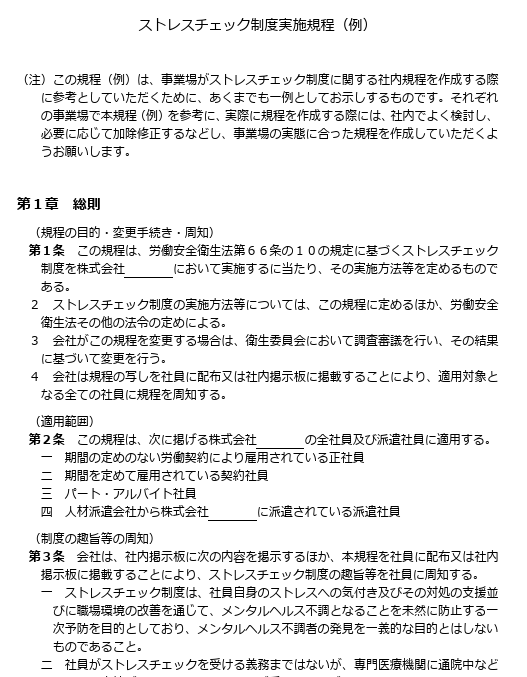
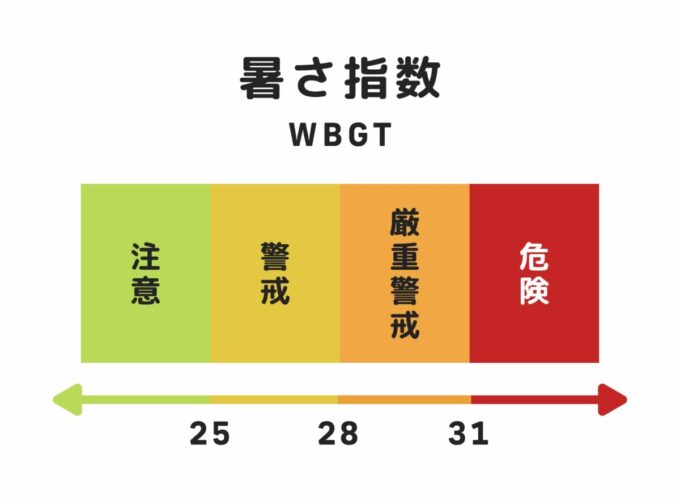
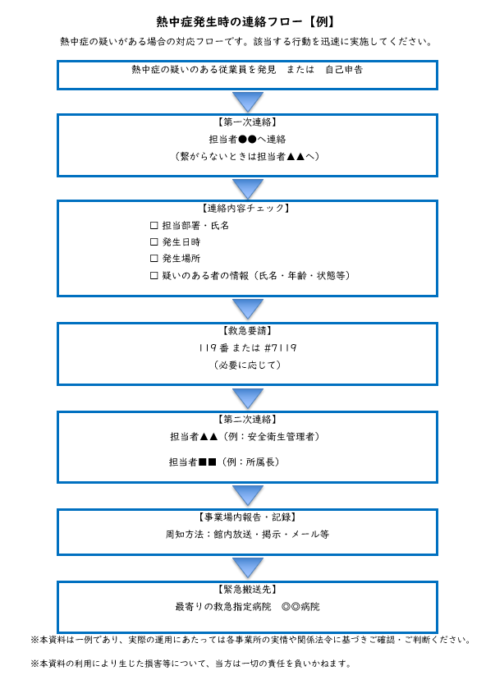
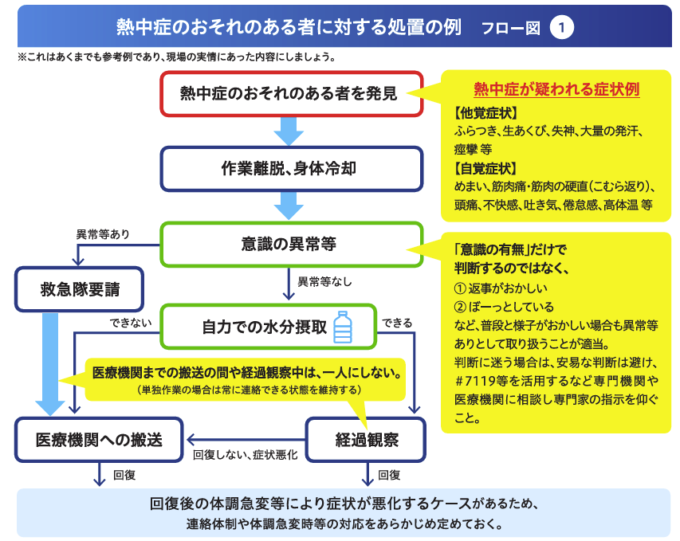
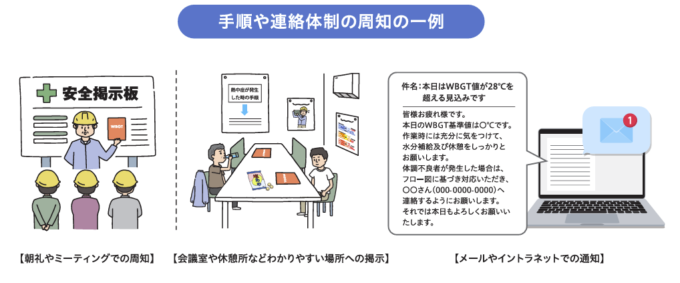
![[ご相談無料]まずはお気軽にご連絡ください。TEL:0120-26-4445[受付時間平日10:00〜21:00(土日祝日は休み)]](https://www.j-consulting.jp/wp-content/themes/theme-yuhara2/img/contact.png)

