下記日程で開催致します。
5月28日 15時、16時、17時、18時
5月29日 11時、14時、15時、16時
5月30日 11時、14時、16時、18時、19時、20時
場所 当社 六本木オフィス
下記までにお申し込み下さい。
メール office@j-consulting.jp
助成金 個別無料相談会(東京)
新助成金について⑵
実習型が4月20日、
被災者雇用開発が5月2日
に正式にスタートしていますが、
その前に採用されている場合は
対象になりません。
企業が早く採用しすぎたのか、
政府の対応が遅いのか、
どちらのでしょう?
後者だと思いますが。
新助成金について
お電話でお問い合わせをかなりいただいています。
本日、明日とも相談受けれますので
下記までお問いあわせ下さい。
携帯電話 090-6876-0999
もしくはメール office@j-consulting.jp
なお、実習型も被災者雇用開発助成金も
ハローワークからの紹介のみです。
保険料関係の免除がきまりました
いずれ通知が来るのでしょうが、
厚生労働省が保険料等の免除を発表しましたね。
「賃金の支払いに著しい支障が生じている等の場合」
と記載があります。
「著しい」とはどの程度か?
「等」とは何が他にあるのか?
わかりましたら報告します。
新助成金発表!!
被災者雇用開発助成金といいます。
5月2日以降の雇用によります。
先に発表されて既に実施されている
実習型助成金との違いは主には下記の3点でしょうか
1、職務経験は問わない(経験者でも未経験者でも可)
2、短時間労働者(20時間以上30時間未満)も該当
3、支給額
実習型は6カ月60万円、6カ月50万円、6カ月50万円 計1年半で160万円
この助成金は、
短時間労働者以外 6カ月45万円、6カ月45万円 計1年で90万円
短時間労働者 6カ月30万円、6カ月30万円 計1年で60万円
(中小企業)
支給額は少なくなりますが(といっても他の助成金と比べても決して悪くはありません)
要件がかなり緩いです。(私の記憶では今までで一番緩いです)
従業員を募集しています 2
履歴書が10人分ほど来ています。
今週中には休みを利用して面接を
全部しようと思います。
いい人がいればいいですね。
助成金が該当するので、毎月平均で
8.8万程出ます。
助かりますね。
従業員を募集しています
履歴書が10人分ほど来ています。
今週中には休みを利用して面接を
全部しようと思います。
いい人がいればいいですね。
助成金が該当するので、毎月平均で
8.8万程出ます。
助かりますね。

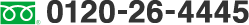
![[ご相談無料]まずはお気軽にご連絡ください。TEL:0120-26-4445[受付時間平日10:00〜21:00(土日祝日は休み)]](https://www.j-consulting.jp/wp-content/themes/theme-yuhara2/img/contact.png)

