【労務管理】家族従業員の労働者性
中小企業や個人事業では、配偶者や子ども、親など、事業主の家族が一緒に働くことは珍しくありません。
しかし、「家族だから労働基準法は関係ない」「給与は手伝いのお礼」といった認識でいるとトラブルにつながることがあります。
家族であっても、「同居の家族以外の従業員を雇っているか」「指揮命令関係があるか」「他の労働者と同じように管理されているか」といった実態によって労働者性を判断する必要があります。
労働基準法上の扱い
労働基準法は、使用者が労働者と雇用契約を結ぶにあたって最低限の基準を設けたものです。
本来、使用者と労働者は「対等な立場」で自由に契約を行うのが原則ですが、労働者は経済的に弱いため、不公平な契約を結んでしまうおそれがあります。そのため、法律で最低限の基準が定められています。
労働基準法では、労働者の定義を「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」と定めています。
第9条(定義)
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
一方で、労働基準法第116条第2項では、「この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない」としており、適用除外を定めています。
つまり、「働いている人が同居の家族だけ」で行う事業であれば、労働基準法の規定(労働時間、休日、割増賃金など)は原則として適用されません。
第116条(適用除外)
②この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。

しかし、ここで注意が必要なのは、同居の親族ではない従業員を1人でも雇っている場合、その事業全体に労働基準法が適用されるということです。
アルバイトやパートの方を1人でも雇っていれば、同居の親族にも労働基準法が適用される場合があるということです。
労働基準法上の「労働者」に該当するかを判断する基準
労働基準法の労働者性は、「使用従属性」によって判断されます。
- 他人の指揮監督下において労働をしているか
- 報酬が「指揮監督下における労働」の対価として支払われているか
この具体的な判断基準は、労働基準法研究会報告(労働基準法の「労働者」の判断基準について)(昭和60年12月19日)において、次のように整理されています。
「指揮監督下の労働」であることの判断要素
- 仕事の依頼、業務従事の指示等に対して諾否の自由があるか
- 業務の内容や遂行方法について具体的な指揮命令を受けているか
- 場所や時間の拘束性はあるか(拘束がある場合、業務の性質上か、指揮命令の必要によるものか)
- 労務提供の代替性はあるか(本人が自らの判断で他の者や補助者を使うことが認められているか)
また、報酬に関して、欠勤控除や残業手当がある場合は、使用従属性を補強するものとして考えられます。
使用従属性の判断が困難な場合に追加で考える要素
使用従属性の判断が困難な場合、次の要素も考慮して総合判断するようになります。
(1)事業者性の有無
本人が所有する著しく高価な機械、器具を使用しているか、事業者として正規従業員よりも著しく高額な報酬を得ているか、損害責任を負っていたり独自の商号を使用したりしているか
(2)専属性の程度
他社の業務に従事することが制度上制約されていたり、時間的余裕がなく事実上専属となっており、経済的に従属しているか、報酬に固定給部分があるか
(3)その他
選考基準、報酬の支払い(給与所得かどうか)、労働保険や服務規律の適用などが判断を補強するものとなります。
労災保険の扱い
労災保険は、労働者が業務または通勤に起因して負傷・疾病・障害・死亡した場合に、政府が保険給付や社会復帰支援を行う制度です。
労災保険の対象者は原則としてアルバイトやパートタイマー等を含むすべての労働者です。
事業主と同居の親族は、原則として労災保険の対象外
事業主と同居の親族は、原則として労災保険の対象にはなりません。
ただし、常時、同居の親族以外の労働者を使用している事業で、同居の親族が下記の条件を満たし、一般事務や現場作業などに従事している場合は、私生活とは別に独立した労働関係が成立しているとみなされ、労災保険の対象となります。
実態として労働者であることの要件
- 明確に事業主の指揮命令に従って業務を行っている
- 同居の親族ではない労働者と同じように働き、労働時間や休憩、休日等の管理をされていて、賃金も労働に応じて支払われている。
雇用保険の扱い
個人事業主や実質的に個人事業と同様の法人の事業主と同居している親族は、原則として雇用保険に加入できません。家族としての協力関係が強く、使用従属関係が不明確になりやすいためです。
しかし、以下の要件をすべて満たす場合は加入が認められます。手続きの際は、ハローワークに実態を確認できる書類等を提出する必要があります。
同居している親族が雇用保険に入る要件
- 明確に事業主の指揮命令に従って業務を行っている
- 他の労働者と同じように就労していて、勤怠の管理を受けており、賃金もこれに応じて支払われている
- 役員など、事業主と利益を一にする地位ではないこと
例えば、他の従業員と同じように出退勤の打刻やシフト管理をされており、給与計算も同じ方法で行われていれば、雇用関係が認められる可能性があります。
逆に、「必要な時だけ手伝う」「給与は月ごとに任意で支給」などの場合は、要件を満たさないことになります。
会社設立・会計・労務・労働者派遣・助成金・融資・起業・許認可などの経営相談はアントレグループ
TEL 0120-26-4445 受付時間 平日・土曜日 9:00~19:00(日祝は休み)
お問い合わせはこちらから
- [東京オフィス]〒107-0052 東京都港区赤坂9-1-7 秀和赤坂レジデンシャル255号
- [仙台オフィス]〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-1-58 ダイアパレス仙台中央615号
- [泉中央オフィス]〒981-3133 仙台市泉区泉中央3-19-11 ロイヤルヒルズ赤坂202号
- [長町オフィス]〒982-0011 仙台市太白区長町一丁目7番28号 ライオンズマンション長町一丁目2階

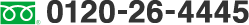
![[ご相談無料]まずはお気軽にご連絡ください。TEL:0120-26-4445[受付時間平日10:00〜21:00(土日祝日は休み)]](https://www.j-consulting.jp/wp-content/themes/theme-yuhara2/img/contact.png)

